電子音楽 WEB制作(HP制作)
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
採用活動 TikTok動画で求人募集につなげる
人事担当者や経営者の方から、このような悲鳴にも似た相談を日々受けます。 Indeedやリクナビなどの媒体に高い掲載費を払っても、効果が薄れてきている。そう感じていませんか?
それもそのはずです。求職者の行動様式は劇的に変化しました。彼らはもう、美しく整えられた求人原稿を信じていません。彼らが探しているのは、企業の「リアル(素顔)」です。
そこで今、採用の主戦場となっているのがTikTokです。 「TikTokで採用? 若者が踊っているだけでしょ?」 もしそう思っているなら、その認識が採用難の根本原因かもしれません。
今回は、Webマーケティングと動画制作の視点から、TikTokを単なるエンタメではなく、最強の「採用オウンドメディア」に変えるための戦略について解説します。 これは、流行りの話ではなく、企業の存続に関わる人材獲得の生存戦略です。
採用活動は「マーケティング」そのものです
まず、採用に対する意識を少し変えてみましょう。 採用活動とは、「自社」という商品を、「求職者」という顧客に売り込むマーケティング活動そのものです。
従来の求人媒体は、言うなれば「他人の土地で商売をさせてもらっている」状態です。 高い出店料(掲載費)を払い、画一的なフォーマットで、競合他社と横並びにされる。これでは、資金力のある大手企業には勝てません。
しかし、TikTokや自社ホームページを使った採用活動は違います。 そこは「自社の土地」です。表現の自由度が高く、熱量をそのまま伝えることができます。
Webマーケティングの世界では、自社のメディア(オウンドメディア)を持つことが最強の資産となりますが、採用においても全く同じことが言えるのです。
なぜ今、テキストではなく「動画」なのか
求職者が企業を選ぶ際、最も不安に感じていることは何でしょうか? 給与や待遇も大切ですが、最終的な決め手になるのは「自分はこの会社でやっていけるか?」という直感的な安心感です。
「職場の雰囲気」「社員の人柄」「オフィスの空気感」 これらのような「非言語情報」は、どれだけ優れたコピーライティングでも、テキストと静止画だけでは伝えきれません。
1分の動画が伝える情報量は、Webページ3,600ページ分に相当するとも言われます。 TikTokのショート動画なら、社員同士の何気ない会話や、休憩時間の様子、あるいは社長の意外な一面などを通して、企業の「温度感」をダイレクトに伝えることができます。
この「温度感の共有」こそが、求職者の不安を取り除き、応募へのハードルを劇的に下げるのです。
「ミスマッチ」を防ぐフィルターとしての機能
採用担当者を悩ませるもう一つの問題が「ミスマッチ」です。 苦労して採用したのに、「思っていたのと違った」と言ってすぐに辞めてしまう。これは企業にとっても求職者にとっても不幸なことです。
TikTok動画は、このミスマッチを防ぐ強力なフィルターになります。
例えば、あえて「仕事の厳しさ」や「泥臭い現場」を見せることも戦略の一つです。 綺麗なオフィスで優雅に働くイメージを持っていた人は応募してこないかもしれません。しかし、「その厳しさこそが成長につながる」と共感してくれる、骨のある人材だけが集まるようになります。
「良いことばかり言わない」 この誠実な姿勢が、結果として定着率の高い、質の良い母集団形成につながります。
踊る必要はありません。「日常」がコンテンツです
「TikTokをやるなら、社長や社員が踊らないといけないんでしょうか?」 よく聞かれますが、その必要はありません。(もちろん、社風に合うならOKですが)
求職者が見たいのは、作り込まれたダンスではなく、そこにある「日常」です。
ランチタイムにどんな会話をしているのか
会議の雰囲気はピリピリしているのか、和やかなのか
残業している社員に「お疲れ様」と声をかける文化はあるか
こうした何気ないシーンこそが、求職者にとっては喉から手が出るほど欲しい情報です。 かっこつける必要はありません。ありのままの姿を切り取るだけで、それは立派な採用コンテンツになります。
TikTokからホームページへの「採用導線」
Webマーケティングのプロとして最も重要な「導線設計」の話をします。
TikTokで興味を持ってもらった後、どうするか。 ここで満足させて終わってはいけません。必ず、プロフィールのリンクから自社の「採用サイト(ホームページ)」へ誘導してください。
TikTokはあくまで「興味付け(認知)」の入り口です。 詳しい募集要項や、代表メッセージ、先輩社員のインタビューといった深い情報は、ホームページでしっかりと読んでもらう必要があります。
この「TikTok(動画)→ ホームページ(詳細情報)→ 応募」という流れをスムーズに作ることが、採用成功の鍵です。 動画で感情を動かし、ホームページで理性を納得させる。この両輪が回って初めて、求職者は「応募する」というアクションを起こします。
TikTokは単なる遊び道具ではありません。 使い方次第で、広告費をかけずに優秀な人材を引き寄せ続ける、強力な「採用エンジン」になります。 まずはスマホを片手に、オフィスの日常を撮影することから始めてみてはいかがでしょうか。 その一歩が、会社の未来を変える出会いにつながるかもしれません。
採用活動がうまくいかない人事担当者へ TikTok動画で求人募集につなげるポイント
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
ドメイン・URLの変更
ホームページのドメイン(URL)を変更する場合の作業
ホームページのドメイン(URL)変更を行う場合は、DNSの反映時間等を含め、見落としている点はないかを常に確認し、慎重に作業をしていく必要があります。ドメインを変更するとホームページのアドレスが変更になるため、全てのページで以前のURLが利用できなくなります。
ドメイン変更があるとリダイレクト設定も必要ですし、被リンクの力も弱まります。
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
「広告をクリックしたのに売れない」その原因はここにあります。業種別・勝ち抜くためのLP構成と情報設計の鉄則
SNS広告とランディングページ連携による広告費の有効活用について
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
誰も通らない路地裏に「最高の店」を建てていませんか?ホームページを「看板」として機能させるための最初の一歩
誰も通らない路地裏に「最高の店」を建てていませんか?ホームページを「看板」として機能させるための最初の一歩
「素晴らしい技術があるのに、なぜか注文が来ない」 「こだわりの商品を揃えているのに、お客様に知られていない」
もし今、事業においてそのようなもどかしさを感じているのであれば、一度立ち止まって、自社のホームページ(ウェブサイト)の「あり方」を見つめ直してみてください。
まず皆さんに考えていただきたいのは、ホームページが果たしている本来の役割についてです。
多くの人が、ホームページを「会社案内」や「電子カタログ」のように捉えています。もちろんその側面はありますが、事業を行う上で最も重要な役割は、お店における「表に出ている看板」や「店構え」そのものです。
現実世界で考えてみてください。どんなに腕の良いシェフがいて、どんなに美味しい料理を提供するレストランでも、人通りのない路地裏にあり、看板も出ておらず、入り口がどこかもわからない状態でお客さんが来るでしょうか。おそらく、たまたま迷い込んだ人以外は誰も来ないでしょう。
インターネットの世界もこれと全く同じです。
どんなにデザインが美しくても、どんなに素晴らしい商品やサービスを掲載していても、検索エンジニアという「道」を通る人々に見つけてもらえなければ、そのホームページは存在していないのと変わりません。
だからこそ、ホームページ運営の出発点は、デザインを凝ることでも、アニメーションを入れることでもなく、まずは「検索されやすい状態」に整えること。つまり、お店の前にお客様を連れてくる導線を作ることなのです。
今回は、多くの人が難しく考えすぎてつまずいてしまう「SEO対策」の第一歩について、プロフェッショナルな視点から、極めてシンプルかつ本質的なお話をします。
SEO対策とは「Googleへの接待」ではなく「お客様への親切」です
「SEO対策」という言葉を聞くと、何か特殊な技術を使ってGoogleの裏をかくような、小難しいテクニックを想像される方が多いかもしれません。
しかし、私たちトップレベルのマーケターが考えているSEOは、もっと人間味のあるものです。
SEO(検索エンジン最適化)の本質は、検索エンジンを使っているユーザーに対して、「あなたの探している答えはここにありますよ」と分かりやすく提示してあげること。つまり、ユーザーに対する「おもてなし」や「親切心」そのものです。
道に迷っている人に、「美味しいイタリアンなら、あそこの角を曲がったところにありますよ」と看板を出してあげる。これがSEOです。
GoogleのAIは年々進化していますが、彼らが目指しているゴールも「ユーザーが探している情報を、最短で届けること」です。ですから、私たちがやるべきことは、Googleの顔色をうかがうことではなく、画面の向こうにいるお客様がどんな言葉で検索し、何を求めているのかを想像することなのです。
まず決めるべきは「誰に、どうやって見つけてもらうか」
ここで多くの担当者が悩み、「SEO対策って結局何をしたらいいのかわからない」と思考停止してしまいます。
専門的な内部構造の改善や、被リンクの獲得といった高度な施策は、プロである私たちに任せていただければ結構です。まず皆さんが最初に取り組むべきことは、もっとシンプルです。
それは、「検索されたいキーワード」を決めることです。
自分たちの会社やお店は、どんな言葉で検索された時に、検索結果の一番上に表示されたいでしょうか。これを決めずにホームページを作るのは、行き先を決めずに航海に出るようなものです。
「地域名+サービス名」は最強の基本戦略
キーワード選びで迷ったら、まずは基本中の基本である「地域名+サービス名」の組み合わせから始めてください。
例えば、あなたが渋谷で美容室を経営しているなら「渋谷 美容室」。 大阪で税理士事務所を開いているなら「大阪 税理士」。 横浜で外壁塗装を行っているなら「横浜 外壁塗装」。
なぜ、この組み合わせが重要なのでしょうか。 それは、この検索キーワードを使うユーザーは、「今すぐそのサービスを利用したい」と考えている可能性が極めて高いからです。
単に「美容室」とだけ検索する人は、全国のヘアスタイルのトレンドを見たいだけかもしれません。しかし、「渋谷 美容室」と検索する人は、渋谷に行く予定があり、そこで髪を切りたいと思っている人です。つまり、具体的なお客様になる確率(コンバージョン率)が高いのです。
大手企業がひしめく「美容室」というビッグワード単体で検索上位を取るのは至難の業ですが、「地域名」を掛け合わせることで、競合が絞られ、中小規模の事業者でも十分に戦える土俵になります。
自社のホームページ(ウェブサイト)のタイトルタグや、トップページの見出しに、この「地域名+サービス名」がしっかりと入っているか。まずはそこを確認するだけでも、大きな第一歩です。
プロの専門用語と、お客様の日常用語のズレに気づく
キーワードを決める際に、もう一つ注意していただきたいポイントがあります。それは、「プロの言葉」と「素人の言葉」のズレです。
私たちは無意識のうちに、業界の専門用語を使ってしまいます。 例えば、工務店の方が「注文住宅」という言葉で上位表示を狙っているとします。しかし、家を建てたいと考えているお客様は、「注文住宅」という言葉を知らずに、「一軒家 おしゃれ」や「マイホーム 設計」と検索しているかもしれません。
歯科医院であれば、「インプラント」という言葉を知らない患者さんは、「歯 埋め込む」や「入れ歯 代わり」と検索するかもしれません。
自分たちが「伝えたい言葉」ではなく、お客様が「使っている言葉」を選ぶこと。
この視点が抜け落ちていると、いくらSEO対策をしても、誰とも出会えません。普段、お客様とお話しする中で、彼らがどんな単語を使っているか、耳を澄ませてみてください。そこに、お宝キーワードが眠っています。
看板を掲げたら、中身を整える
適切なキーワードを選び、ホームページ(ウェブサイト)のタイトルや説明文に盛り込むこと。これが「看板を掲げる」という作業です。
しかし、看板を見て店内に入ってくれたお客様が、中を見てガッカリしてすぐに出て行ってしまったら意味がありません。
「地域名+サービス名」で検索して来てくれたお客様は、何を知りたいでしょうか。 料金表、お店の場所、スタッフの顔、過去の実績、お客様の声。そうした情報が、わかりやすく掲載されている必要があります。
検索キーワードは「入り口」であり、ホームページの中身は「接客」です。
「渋谷 美容室 カット上手い」で検索して入ってきたのに、トップページに「スタッフ募集」のバナーが一番大きく出ていたら、お客様は「今は求めていない」と感じて帰ってしまいます。
選んだキーワードと、ページの内容(コンテンツ)が一致しているか。お客様の期待を裏切っていないか。この整合性を取ることが、検索順位を安定させ、最終的な問い合わせにつなげるための重要な要素です。
検索されやすい状態を作ることは、事業への責任です
ホームページを持っているのに、誰にも見られていない。これは、非常にもったいない状態です。それは、あなたの商品やサービスを必要としている人が、すぐ近くにいるのに出会えていないという「機会損失」だからです。
SEO対策は、決して難しい魔法ではありません。「私たちのお店はここにありますよ」「あなたの悩みはここで解決できますよ」と、デジタル空間で手を挙げる行為です。
まずは、自社のホームページを見直してみてください。 看板は出ていますか? その看板には、お客様が探している言葉が書かれていますか?
もし、「何から手をつけていいかわからない」「自分たちでキーワードを選定したが、効果が出ない」という場合は、私たち専門家にご相談ください。
私たちは、単に順位を上げるだけでなく、御社の事業内容やターゲット層を深く理解した上で、最も利益につながる「勝てるキーワード」を選定し、サイト全体の構造を最適化します。
路地裏の隠れ家も素敵ですが、事業を成長させるためには、やはりメインストリートに看板を出す必要があります。インターネットという広大な世界で、御社が正しく見つけられる存在になるよう、私たちが全力でサポートします。
まずは「検索されること」から、すべてを始めていきましょう。
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
インデックス削除は「無価値」の烙印なのか?検索エンジンが求める「オリジナル」の正体と、再評価されるための技術論
これを「意味のないサイトであるという判定」と受け取るのは、ある意味で正解であり、技術的には少し言葉足らずでもあります。
まず、私たちが相手にしている検索エンジンの裏側で何が起きているのか、そのメカニズムを解き明かすことから始めましょう。
インデックス削除が意味する「選別」の現実
「インデックス削除」や「未登録」という扱いは、Googleからの「このページをデータベースに保存するコストをかける価値が見当たらない」という通告です。
インターネット上のページ数は爆発的に増え続けています。一方で、Googleが持っているサーバーの容量や、世界中のサイトを巡回するロボット(クローラー)のリソースには限界があります。無限ではないのです。
そのため、Googleは現在、インデックスさせるページを厳しく選別しています。「保存するに値する情報か」「ユーザーに検索結果として表示する需要があるか」を瞬時に判断し、その基準に満たないものを弾いています。
ここで重要なのは、「あなたが一生懸命書いたかどうか」は判断基準に含まれないということです。
厳しい言い方になりますが、検索エンジンにとっての「意味がある」とは、「検索ユーザーの悩みを解決する新しい情報が含まれているか」だけです。もし、世の中に既に似たような情報が溢れていて、あなたのページがそれらの焼き直し(リライト)に見えるなら、Googleは「この情報は既に持っているから、これ以上保存する必要はない」と判断します。これがインデックス未登録の正体です。
オリジナル性とは「形態素の並び」ではない
では、ご質問にあった「オリジナル性」についてです。「独自の形態素の並び(単語の組み合わせ)」であればオリジナルとみなされるのか。
答えは「NO」です。
かつての検索エンジンであれば、語尾を変えたり、単語を入れ替えたりするだけで「別の文章」として認識してくれました。しかし、現在のAI(GoogleのランキングAI)は、もっと深いレベルで文章を理解しています。
彼らは、文章を単なる文字の羅列としてではなく、「意味のベクトル(方向性)」として捉えています。
例えば、「美味しいカレーの作り方」という記事があったとします。 Aサイト:「まず玉ねぎを飴色になるまで炒めます」 Bサイト:「フライパンで玉ねぎが茶色くなるまで加熱しましょう」
この2つは、形態素(文字の並び)としては全く別物です。しかし、AIはこれらを「意味的に100%同じ情報」と判断します。Web上にAサイトのような情報が既に大量にある場合、Bサイトの記事は「重複コンテンツ」や「付加価値のないコンテンツ」とみなされ、インデックスの優先順位が極端に下がります。
AIが求めているオリジナル性とは、表現の違いではありません。「情報の発生源」としての独自性です。
「玉ねぎを炒めている時に、誤って焦がしてしまったが、それが逆に隠し味になった」という失敗談や、「プロの料理人に聞いた、玉ねぎを3分で飴色にする裏技」といった、あなただけが知っている事実、体験、検証結果。これらが含まれて初めて、AIは「これは保存すべき新しい情報だ」と認識します。
サイト内容の分散は逆効果になるリスク
「サイト内容の分散がオリジナル性を保つことになるのか」という点については、慎重になる必要があります。
もし、一つの大きなテーマ(例えば「Webマーケティング」)について書く際、情報を細切れにして、内容の薄いページを大量に量産する(分散させる)手法をとっているなら、それは逆効果です。
Googleは現在、「トピックの網羅性」と「情報の密度」を重視しています。
スカスカの内容の記事が100ページあるサイトよりも、専門的な知見がぎっしり詰まった記事が10ページあるサイトの方を、権威あるサイトとして評価します。内容を分散させると、一つひとつのページのパワーが弱まり、結果として「低品質なページ(Thin Content)」の集合体とみなされ、サイト全体の評価が下落する可能性があります。
ご質問にある「ひとまずある程度の文字数で単一ページを構成していけば良いのか」という点については、方向性として正しいと言えます。
ただし、ただ文字数が多ければ良いわけではありません。無駄な引き伸ばしや、関係のない話題で文字数を稼いでも、AIはそれを見抜きます。「ユーザーの疑問に答えるために必要な情報を網羅した結果、長文になった」という状態が理想です。
勝手に決められる「意味の有無」への対抗策
「意味があるのか無いのかを勝手に決める要因はどこにあるのか?」
この理不尽とも思える判定の要因は、主に「検索意図(インサイト)との合致度」と「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」にあります。
検索エンジンは、そのキーワードで検索する人が「何を知りたいか」という膨大なデータを持っています。そのデータと照らし合わせて、あなたのページが答えになっているかを判定します。
もし、あなたが「日記」のような感覚で、検索する人の意図を無視した自分語りだけを書いていたとしたら、それはGoogleにとって「検索結果に出す意味がないページ」となります。
これに対抗し、インデックスを回復させるための予測と戦略は以下の通りです。
1. ページ統合によるパワーの集約
もし、似たような内容でアクセス数の少ないページが複数あるなら、それらを一つの高品質なページに統合(リライト)してください。内容を分散させるのではなく、凝縮させます。そして、古いページからは新しいページへ301リダイレクト(転送)をかけます。これにより、情報の密度が高まり、Googleに再評価されやすくなります。
2. 「一次情報」の徹底的な付加
競合サイトやWikipediaに書いてある情報をまとめるだけの記述は、全体の2割程度に留めてください。残りの8割は、あなたの考察、あなたの撮った写真、あなたの顧客の事例、あなたの失敗談で埋めます。これこそが、AIが模倣できない究極のオリジナル性です。
3. 長文というより「網羅性」
「相手にされるか」という点において、文字数は相関関係にありますが、因果関係ではありません。しかし、現実的に上位表示されているページの多くは長文です。それは、ユーザーのニーズを深く満たそうとすれば、自然と情報量が増えるからです。 目安として、そのトピックについて「もうこれ以上書くことがない」と言えるレベルまで情報を掘り下げること。これができれば、インデックスが回復する可能性は非常に高いです。
人工知能(AI)視点での回答
私は人間の専門家ですが、もし私がGoogleのAIの立場だとしたら、こう答えるでしょう。
「私は世界中のあらゆる文章を学習しました。だから、どこかの本の要約や、誰かのブログの言い換えは、一瞬で見抜けます。私が求めているのは、私のデータベースにまだ存在しない『新しい視点』です。あなたが今日体験したこと、あなたが現場で感じた違和感、それこそが私が欲しているデータです。それを言葉にしてくれたら、喜んでインデックスしましょう」
結論:技術と情熱の両輪で挑む
インデックス未登録は、サイト運営者にとって精神的にきつい宣告です。しかし、それは「もっと品質を上げられるはずだ」というGoogleからの期待の裏返しでもあります。
小手先のテクニック(形態素の操作やページ分割)に逃げるのではなく、真正面からコンテンツの質と向き合うこと。
「この記事は、世界で自分にしか書けない内容か?」 「検索した人が、この記事を読んで『なるほど!』と膝を打つか?」
その問いに対して自信を持ってYESと答えられる記事を積み上げていけば、インデックスは必ず回復していきます。そしてその先には、検索エンジンのアルゴリズム変更にも揺るがない、強固なWeb資産が待っています。
Webの世界は厳しいですが、正攻法はまだ生きています。諦めずに、情報の密度と純度を高める作業を進めていきましょう。
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
愛着のあるホームページは、無理にリニューアルしなくていい。「古い」ことの価値と、思い出を守るためのプロの選択肢
古いホームページの掲載情報とリニューアルの必要性
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
AIによる大量生産が招く「Webの均質化」。それでも私たちが、汗をかいて言葉を紡ぐべき理由
「AIを使えば、ブログ記事なんて一瞬で書ける」 「コンテンツ制作のコストが十分の一になった」
ここ最近、そんな声があちこちから聞こえてきます。確かに、ChatGPTをはじめとする生成AIの進化は凄まじいものがあります。キーワードをいくつか投げかけるだけで、ほんの数秒後には、それらしい文章が画面いっぱいに生成されます。
経営者やWeb担当者の方々が、この効率性に飛びつきたくなる気持ちは痛いほどわかります。時間もコストも限られている中で、魔法のようなツールが現れたのですから。
しかし、世界のWebトレンドや検索エンジンの動向を最前線で追いかけている私の立場から申し上げますと、この「AIによるコンテンツの大量生産」は、手放しで喜べる状況ではありません。むしろ、Webという文化そのものを変質させ、私たちが大切にしてきた「情報の価値」を壊してしまう恐れすらあると感じています。
今回は、AIが生み出す記事がWebに何をもたらしているのか、そして、これからの時代に本当に評価されるホームページ(ウェブサイト)とはどのようなものなのか、技術と倫理の両面から深く掘り下げてお話しします。
「どこかで見たことがある」文章で埋め尽くされる未来
インターネットの面白さとは、一体何だったでしょうか。
それは、世界中の多種多様な人々が、それぞれの視点、それぞれの体験、それぞれの言葉で情報を発信していた点にあります。
プロのライターが書いた洗練された記事もあれば、個人の日記のような泥臭い文章もある。専門家の深い知識もあれば、初心者の素朴な疑問もある。この「情報の厚み」や「ノイズ」こそが、Webの豊かさであり、私たちが検索窓に言葉を打ち込む理由でした。
ところが今、その多様性が急速に失われつつあります。
AIが生成する文章は、インターネット上に存在する膨大な過去のデータをもとに、「統計的に最も確からしい言葉の並び」を出力したものです。つまり、AIが書く文章は、本質的に「平均点」の文章にならざるを得ません。
誰からも嫌われない代わりに、誰の心にも深く刺さらない。文法は完璧だけれども、体温を感じない。
皆さんも最近、何かを検索した時に感じたことはないでしょうか。「どのサイトを見ても、同じようなことしか書いていないな」と。
これが、AIによる記事の氾濫が招く「情報の均質化」です。オリジナルな声がかき消され、金太郎飴のように似通ったコンテンツばかりが目につくようになる。結果として、Web全体の多様性が失われ、情報の信頼性までもが削がれてしまうのです。
事業における「平均」は「死」を意味します
この問題を、事業(ビジネス)の視点で考えてみましょう。
ホームページ(ウェブサイト)を持つ目的は、他社との違いを伝え、自社のファンになってもらい、商品やサービスを選んでもらうことにあるはずです。
それなのに、AIを使って「平均的」な文章を量産して掲載することは、自ら「その他大勢」に埋没しにいくようなものです。
AIは、「一般的な正解」を答えるのは得意です。「Webマーケティングとは何か」と聞けば、教科書通りの答えを返してくれます。しかし、あなたの会社がこれまでどんな苦労をしてその商品を開発したのか、あなたのスタッフがどんな想いでお客様に接しているのか、昨日のトラブルをどうやって解決したのか、といった「固有のストーリー」は知りません。
顧客が求めているのは、ウィキペディアのような一般的な解説ではなく、「あなたの会社の見解」であり「あなたの会社の体験」です。
AIが書いた無難な記事で埋め尽くされたホームページは、一見すると綺麗に整っているように見えます。しかし、そこには「顔」が見えません。顔が見えない相手から、人は物を買いたいと思うでしょうか。高額なサービスを契約しようと思うでしょうか。
AIに頼り切るということは、自社のブランドを希薄化させるリスクを背負うことと同義なのです。
検索エンジンも「体験」を求めている
SEO(検索エンジン対策)の観点からも、AIコンテンツの丸写しは危険な賭けです。
Googleは近年、「E-E-A-T」という評価基準を重視しています。これは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取ったものです。
ここで注目すべきは、最初にある「Experience(経験)」です。
「実際にその製品を使ったことがあるか」「実際にその場所に行ったことがあるか」「実際にそのトラブルを解決したことがあるか」。Googleは、AIには絶対に真似できない「人間だけが持つ一次情報」を高く評価すると宣言しています。
AIは、データの海を泳ぐことはできても、現実世界で雨に濡れることも、美味しい料理に感動することも、失敗して落ち込むこともありません。つまり、AIには「経験」が欠落しているのです。
検索エンジンは今、AIが量産した「コピペのような記事」を検索結果から排除しようと、アルゴリズムの調整を続けています。楽をしてAIで記事を量産した結果、サイト全体の評価が下がり、検索圏外に飛ばされてしまったという事例も出始めています。
AIは「筆」であり「書き手」ではありません
ここまで厳しいことを申し上げましたが、私は決して「AIを使うな」と言いたいわけではありません。私自身、日々の業務でAIを使わない日はありません。
重要なのは、「AIに何をさせるか」という役割分担です。
冒頭の投稿にもありましたように、AIの活用自体が悪いわけではありません。例えば、商品ページのスペック表(サイズや重量など)の説明文のように、誰が書いても事実が変わらない部分に関しては、AIは非常に有効です。人間が書くよりも正確で、圧倒的に速いでしょう。
また、定型的な報告書の作成、多言語への自動翻訳、プログラミングコードの生成、あるいはアイデア出しの壁打ち相手として、AIは最高のパートナーになります。
記事作成においても、「たたき台」を作らせるまでなら問題ありません。「〇〇について記事を書きたいから、構成案を3つ出して」と頼めば、論理的な構成を瞬時に提案してくれます。
しかし、そこから先、つまり「肉付け」と「仕上げ」は、人間がやらなければなりません。
AIが出した骨組みに対して、自社の事例を加え、担当者の感想を入れ、独特の言い回しに書き換え、読み手への配慮を込める。
AIをそのまま出力して「完了」とするのが問題なのであり、そこに人の知恵や体験を重ね合わせることで、初めて価値が生まれるのです。
「0から1」は人間、「1から100」はAI
私の考えでは、Web制作における役割分担は次のように整理できます。
「0から1」を生み出すのは、人間の仕事です。 何を伝えるか、誰に伝えるか、どんな感情を呼び起こしたいか。この企画や方向性は、事業への情熱を持つ人間が決めるべきです。
「1から100」に広げるのは、AIの得意分野かもしれません。 決まった方向性に沿って情報を網羅したり、バリエーションを増やしたり、誤字脱字をチェックしたりする作業です。
そして最後の「画竜点睛」、魂を入れる作業は再び人間の手に戻ります。
このサンドイッチ構造を理解せずに、0から100まですべてをAIに任せようとするから、退屈で価値のないコンテンツが生まれてしまうのです。
手間をかけることが「差別化」になる時代
皮肉なことに、AIが進化すればするほど、相対的に「人間が汗をかいて書いた文章」の価値は上がっていきます。
多くの企業が効率化の名の下にAIコンテンツに流れていけば、Web上は似たような情報で溢れかえります。その中で、独自の視点、生々しい体験談、書き手の体温が伝わるような文章を発信し続ける企業は、砂漠の中のオアシスのように際立つ存在になるでしょう。
「手間がかかる」「面倒くさい」と思われるかもしれません。しかし、競合他社がやりたがらない「面倒くさいこと」をやり続けることこそが、最も確実な差別化戦略です。
Webマーケティングの世界には、「コンテンツ・イズ・キング(中身こそが王様)」という言葉があります。
AIが生成したテキストデータは、あくまで「データ」です。それを、読み手の心を動かす「コンテンツ」に昇華させることができるのは、今のところ人間だけです。
言葉を紡ぐことは、思考すること
最後に、もう一つ大切な視点をお伝えします。
文章を書くという行為は、単なる作業ではありません。自社の商品について深く考え、顧客の悩みに思いを馳せ、どう伝えれば喜んでもらえるかを試行錯誤する「思考のプロセス」そのものです。
もし、文章作成をすべてAIに丸投げしてしまえば、私たちは顧客のことを考える時間を放棄することになります。思考を外部化してしまえば、やがて自社の中から「言葉にする力」や「伝える力」が失われていくでしょう。
ホームページ(ウェブサイト)は、会社の鏡です。そこに並んでいる言葉が、借り物の言葉であれば、会社そのものも薄っぺらく見えてしまいます。
不格好でもいい。洗練されていなくてもいい。自分たちの頭で考え、自分たちの言葉で語りかけてください。
AIという強力なエンジンを使いこなしながらも、ハンドルは決して離さない。行き先を決めるのも、景色を楽しむのも、私たち人間です。
そうやって作られたホームページだけが、これからのAI時代においても、人々の信頼を勝ち取り、多様性のある豊かなWebの世界を守り抜くことができると、私は信じています。
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
オウンドメディアを運営しているのに成果が出ない。その「停滞」を打破するために必要なのは、指示書ではなく「実装」です
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
ホームページは「読む」から「体験する」時代へ。動画コンテンツが変える集客と採用の未来
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
ホームページのURL変更は「デジタル上の大移転」です。ドメインが変わる瞬間に失われる資産と、Googleツール再設定の落とし穴
ドメインはインターネット上の「信頼の器」です
公開中ホームページのドメイン・URLの変更
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
ホームページの「困った」を即解決。あえて「単発」で依頼する賢い選択と、修正を「改善」に変えるプロの視点
ホームページ修正の際の費用
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
ドメイン移管失敗
・ドメインの期限が切れている場合
・ドメインの期限が7日以内に切れる場合
・移管元ドメイン登録業者でドメイン登録を行ってから60日以上経過していない場合
ドメイン移管ができない!その失敗、実は「時間」のルールに縛られています
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
チラシ効果低下時のクロスメディア戦略 実務マニュアル
1. 現状確認:チラシ効果が下がったと感じるときに行うべきチェック
2. クロスメディア戦略の基本発想
3. 実務フロー① チラシ改良の基本手順
4. 実務フロー② ホームページ側の調整
5. 実務フロー③ データ収集と改善サイクル
6. 成功事例に学ぶクロスメディア活用
7. 実務フロー④ SNSとの連携による拡張
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
ホームページ制作会社 選び方
「ホームページ制作会社選び(選定方法)で失敗しないために知っておく事」Webデザイナーはホームページデザインに対する「自分のこだわり」を大切にする傾向が強いです。
ホームページ制作会社の選び方
ホームページ制作会社を比較検討しようと思っても、数が多すぎてどの会社を選べばよいのかわかりません。ホームページ制作にどれくらいの費用がかかるのかわからずホームページ作成を依頼する制作業者選びに失敗します。ホームページ制作会社の選び方
ホームページ制作費用が総額でいくらかかるのかを合意しておかないと、あなたが一方的にリスクを被ることになります。いろいろとホームページ制作している会社を比較検討されていることと思います。ホームページの作成方法. レンタルサーバーとは何か、ホームページ制作会社とは何なのかということを整理してみましょう。
ホームページ制作の「総額」が見えないリスクと、正しい依頼先の選び方
ホームページの一括見積りの是非
ホームページの一括見積りという概念は、同じようなものをいかに安く発注するかという発想が根底にある。また、人に提案させようという意図が見える。しかし、そうした形で仕事を欲しがっている業者が価格競争をしても、ホームページ制作の結果は千差万別となるため、あまり良い結果は生まれないと考えられる。
エンジニア向けメディアの立ち上げ、運用コンサルティング
オウンドメディアのPV数をUPするだけでなく、出版社の視点から、メディアに取材を受けやすい、露出しやすい、サービス・商品の見せ方を特に得意としており、クライアント様から高い評価
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
ホームページ(サイト)のCSS(スタイルシート)編集の方法
ホームページ(サイト)のCSS(スタイルシート)編集の方法
ホームページ(サイト)は基本的にHTMLで構成され外観・デザインを設定するのはCSS(Cascading Style Sheets)・スタイルシートで設定されています。CSS(Cascading Style Sheets)はスタイルを実行するための言語やスタイルに関する連鎖的な記述を意味し、スタイルシートは、HTMLの外観・体裁(スタイル)を定義するものを意味します。
ページの基本構成はHTMLで、レイアウトやカラーの設定といった外観面はCSSで設定されています。ホームページ修正の基本はこのHTMLとCSSの編集で行います。
編集対象CSSファイル、HTML(インラインスタイルの場合)をダウンロード
CSS・スタイルシート編集を実施
CSSの基本構造としては、適用対象のHTMLタグやid、classを記述し(セレクタ)、プロパティ指定(プロパティとプロパティ値の設定「幅は何px」等)を行います。CSS編集において、新しいセレクタとしてidやclassを設置した場合は、HTML側においてその「CSS指定を適用する部分」を指定する必要があります。
修正編集したCSSファイル等をアップロード
「CSS」は主にHTMLとは独立したCSSファイルを中心に、連続・連鎖的に記述されたスタイル定義・指定を指しますが、スタイルシートは、スタイルに関する定義・指定のすべてを指します。
Webデザインの裏側:プロが教えるCSS編集の実践と「壊さない」ための鉄則
ホームページのCSS・スタイルシート編集方法
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
ホームページ(ウェブサイト)の保守管理、作業内容
ホームページの保守とは、「ホームページの正常な公開状態を保つこと」を意味し、「ホームページが正常に表示され、様々な機能が正常に動作している状態を保つこと」がホームページの保守です。
ホームページの種類によって保守内容は異なります。
静的HTMLサイトの場合は、特に変更のないデータを保存しておけば良い
WordPress等CMSの場合やECサイトなど複雑なシステムを導入している場合は、保守・メンテナンス作業の範囲は広くなる
メールフォーム等を利用している場合、それが正常に動作しているかを確認するということも必要
ページコンテンツが正常表示されているかというところもたまにはチェックする必要がある
ホームページ保守全体
ドメイン(URL)・SSL関連の保守
サーバー関連の保守
ホームページ(ウェブサイト)の保守
ホームページの種類に応じて異なりますが、ホームページ(ウェブサイト)自体の保守は次のような内容です。
サイトデータバックアップ
各種バージョンのバージョンアップ
動作チェック
動作停止の場合の修正・代替措置
WordPressサイトであれば、フルバックアップ後のバージョンアップが基本的な保守作業となります。不具合が生じた時には、バックアップからの復元や一時的なバージョンダウンなどを実施する必要があります。
ホームページの「種類」で変わる保守の急所。バックアップとアップデートの先にある、プロの運用管理術
ホームページの保守・メンテナンスの必要性
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
MEOの共通原則
NAPの一貫性と構造化データ
Name(名称)、Address(住所)、Phone(電話番号)の一貫性は、業種を問わずMEOの基礎である。これらはGoogleのエンティティ認識における「信頼度」の根幹を成しており、GBPだけでなく、公式サイトやポータルサイトにおいても完全一致させる必要がある。
さらに、構造化マークアップ(JSON-LD形式のLocalBusinessスキーマ)によって、検索エンジンに対して明示的にビジネス情報を送信することで、エンティティ同定とローカルアルゴリズムのトラストスコア上昇に寄与する。
GBPカテゴリとセカンダリ設定の最適化
多くの中小事業者はGBPのカテゴリ選定を「とりあえず選ぶ」にとどめているが、メインカテゴリとサブカテゴリの適切な設定は、ローカルパック表示の根幹を左右する。たとえば、美容室であっても「女性専門美容院」「ヘアトリートメントサービス」などのセカンダリカテゴリを設けることで、特定インテント検索での表示機会を増やせる。
エンゲージメント指標の強化(写真、投稿、クチコミ)
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
ホームページ修正の際の費用
ホームページのページ更新やページ追加、ホームページ内部の様々な箇所の修正など、各種ホームページの更新・ホームページの修正に対応。
ホームページ修正の費用
ホームページの修正にあたり、価格表の数値の変更や掲載文章の修正など、軽微なページの掲載内容の編集にも対応画像設置などによって、ページ内のレイアウト変更が必要な場合は別途お見積。背景、フォントカラーの調整も可能。カラー修正や微妙なカラー調整も対応いたします自社では修正できないホームページの修正。ホームページを修正・更新したいが自社では作業できない、簡単な更新はできるがホームページ修正で難しいことはできない。
ホームページ内の画像設置、リンク設置・修正、レイアウト変更、ホームページのヘッダー情報(メタ設定)など、各種既存ページの修正に対応可能。ホームページの修正を小さなもの1点から。
ホームページ修正を依頼する時は、単発のホームページ修正依頼がいい。ホームページのレイアウト崩れやスマートフォン表示に未対応のページのスマホ対応、メールフォームのエラー復旧など、各種ホームページのエラーに対応
修正ディレクター
狙ったキーワードで上位かが狙える内容になっているか、ユーザーニーズを満たしているかなど、細分化されたチェック項目に基づいて品質を管理しております。コンサルレベルの知識を有したディレクターチーム。効果的なキーワードの選定や競合調査など、SEOのコンサルタントが行う業務も弊社では代行可能です。ホームページ修正に合わせた記事作成代行サービス
WEB制作・修正と合わせた保守運用
WEB制作と合わせて保守運用を受託しているがリソースが足りない企業様。
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
古いホームページの掲載情報とリニューアルの必要性
さらに、古いホームページは、改ざん等のセキュリティリスクやWebマーケティング効果の低下といった面があるため、リニューアルした方が良いというのも事実です。
マーケティングのためにホームページを運営しているという面はありながら、そのホームページには思い出が詰まっているという場合もあります。長期間運営されている場合はその傾向があります。古いホームページのリニューアルにまつわるコンテンツ(記事)は、リニューアルの必要性、リニューアルしないことのデメリットばかりが掲載されていますが、現状のホームページに思い入れがある場合がある場合、Webデザインが古いからといってそのホームページをリニューアルする必要はないと思っています。
長期間運営している古いホームページのリニューアル
リニューアル内容はどのようなものが良いか?
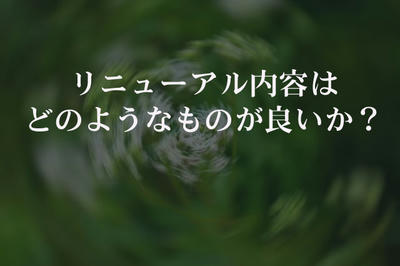
リニューアル内容はどのようなものが良いか?古い ホームページから新しい ホームページにする時、どのような点に気をつければよいか?
やはりそれは相手の中に眠っている可能性をどれだけ引き出すかという点です。
自分たちが用意したものに相手を無理にはめ込もうとすると抵抗が生まれます。
相手の中の可能性を引き出し、導き、その先に商品やサービスを置くということです。
当たり前のことを当たり前に語ると、検索においても人工知能に弾かれます。
そして相手の心に響きません。
不器用でも構いません。
表現したいものを表現してください。
腕利きのWebデザイナーに美しいウェブサイトを作って貰う必要はありません。
見栄えはきれいで中身のないものになるのならばそうしたリニューアルは意味がありません。
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
ホームページ集客方法を絞込む
ホームページ集客方法にはたくさん方法論が存在するが、企業の業種や地域特性、ターゲット層などによって効果的な方法はそれぞれ異なる。ホームページの集客力をアップするためにどんなことをすればいいのか。
ホームページの集客方法は無数にありますが、BtoBと店舗の違い、企業の特性、事業の大きさ、地域性など、様々な特徴に合わせて、有効なものと、費用対効果が見合わないものがある。
ホームページ集客で成功するための方法。
ホームページ集客方法
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
公開中ホームページのドメイン・URLの変更
ドメイン(URL)を変更する場合は、どのような場合でもサイトデータの移管やサイト内URLパスの変更、SEOのためのリダイレクト処理等の他、メールアドレスの再設定なども必要になります。こうしたホームページのドメイン(URL)の変更について触れていきます。
ホームページのドメイン(URL)変更
ホームページ(ウェブサイト)のドメイン変更についてですが、これはホームページのアドレス(URL)の変更です。このドメイン変更には、独自ドメインから別の独自ドメインへの変更といった場合と、サブドメインから独自ドメインへの変更といった場合など様々なパターンがあります。
必要な作業としては、いずれの場合でもさほど変わりありません。しかし、レンタルブログ・レンタルホームページ内で有料プランを利用し、サブドメインやサブディレクトリから独自ドメインへとサイトURLを変更する場合には、さほど手間はかからない場合があります。
ドメイン(URL)を変更する場合はサイトデータの移管やサイト内URLパスの変更、SEOのためのリダイレクト処理等の他、メールアドレスの再設定なども必要になります。
ホームページのドメイン(URL)変更
データの移管やドメイン(URL)変更後のSEO
ホームページのドメイン(URL)変更に伴い、サイトデータの移管が必要になる場合があります。主に、別サーバーで別ドメインで運用を始める場合です。
この場合は、ホームページ(ウェブサイト)のすべてのデータを移管し、かつ、URLパス等を書き換える必要があります。
また、ホームページのドメイン(URL)を変更する場合、SEOの面からの対策、対応が必要になります。理屈の上では、別ドメインで公開されているホームページは、別のホームページです。それを「ドメイン変更により移転した」ということを検索エンジン等に知らせていく必要があります。
ホームページのURL、ドメインの変更は、単なる「住所変更」ではありません。表面的にはアドレスが変わるだけのように思えますが、裏側では多くのシステムが連携し、各種解析や集客、外部ツールとの通信が成り立っています。ドメインを変更することにより、これらの連携が途切れたり、誤作動を起こしたりするリスクがあるため、慎重な再設定が求められます。最も影響が出やすいのはGoogleが提供する各種の無料ツールです。例えばSearch Console、Google Analytics、Google Tag Managerなどは、ドメインをキーとしてサイトの認識やデータの蓄積を行っています。これらは旧ドメインの設定とは別に、新しいドメイン用として再構築する必要があります。
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
ホームページ自体を削除する
削除後も何かしらの理由でそのホームページやホームページ内のデータを利用する可能性がある場合は、バックアップを取っておいたほうが無難です。レンタルブログ等の削除に関しては、対象サービスの管理画面で削除作業を行います。
公開中のホームページの削除や一部ページの削除
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
HTML編集 編集対象であるHTMLファイルをダウンロード【ホームページ制作業務】
場合によっては、サーバコントロールパネル経由でファイルマネージャに移動し、ファイルマネージャ上で対象HTMLファイルをダウンロードします。
ホームページ制作業務
ホームページ制作業務は無料のホームページ作成ツールである程度素人でもできる。問題は集客とコンバージョン。ホームページ制作を行うことができても、人を呼び込み、それを見た人が行動を起こすという導線が重要になる。
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
「画像インデックス化」は、構造化データとの連携によって強化できる
特に製品画像であれば、schema.orgのProductマークアップにimageプロパティを明記することで、Google ShoppingやDiscoverとの連携が容易になり、画像検索結果での視認性が飛躍的に高まります。
これにより、単なる画像露出から「クリック率の高いメディア要素」へと格上げすることが可能になります。
画像のSEO最適化とロスレス圧縮は、単体の技術施策というよりも、パフォーマンス最適化・ユーザー体験・インデックス設計・クロール効率・アクセシビリティといった複数領域の交点にあるものです。
そのため、個別のページ単位ではなく、サイト全体の構造と方針に基づいて統一的な戦略として設計し、技術スタックや運用フローに組み込む必要があります。
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
ホームページ常時SSL化(https化)の依頼
ホームページがWordPressサイトであるかどうかやサーバーサイドでSSL証明書の発行の取扱などによってSSL化(https化)にかかる費用は変動。
ホームページ常時SSL化(https化)の依頼
非SSL(http)ホームページのSSL化(https化)
ホームページのSSL化(https化) の費用と依頼。既存ホームページをSSL化(https化) する際の依頼における費用など。
SSLによってhttps通信されているホームページとhttpで通信されているホームページを比較した場合、常時SSL化され、httpsで通信されているホームページの方が検索順位においても優先される。
SSLとは
SSLとは、サイト接続に関する暗号化通信でSSL(Secure Sockets Layer)。SSLを導入することで、ホームページ閲覧の通信を暗号化することができる。常にホームページを暗号化通信する常時SSLを導入することにより、メールフォームなどの利用時の個人情報を保護することができるようになる。
httpホームページをhttpsホームページへと変更する場合、Let'sEncryptなどのSSL証明書を発行するだけでは完了しない。ホームページ内のURLをhttpsへと書き換えたり、httpへのアクセスをhttpsへと転送したりなどの実作業が必要になる。
電子音楽制作とウェブサイト制作(ホームページ制作) たまに楽器
最新記事
ホームページ制作Web関連
ホームページ制作・WordPressなどのWeb関連。 ホームページ制作会社・Web制作会社
Web制作
・ホームページ制作 Web制作 ・Webマーケティング ・SEOコンサルティング ・SEOライティング ・MEO ・Webサイトリニューアル設計 ・Webサイト保守・運用
